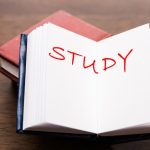みなさんは普段、「不徳の致すところ」という言葉を見聞きしたり使ったりしますか?
最近、よく芸能人が不祥事を起こした際に記者会見などで「不徳の致すところ」と言っているのをよく聞く気がしますね。
そんな本日は「不徳の致すところ」の意味と正しい使い方、類義語や例文を詳しく解説していきたいと思います。
「不徳の致すところ」の意味は?
まず、最初に「不徳の致すところ」の詳しい意味を見ていきましょう!
「不徳の致すところ」は、慣用的な表現で、「不徳」、「致す」、「ところ」の3要素から成り立っています。
まず「不徳」は、「徳」という言葉を否定する形の語句です。
「徳」とは、元来は「祭壇に上がる」という状況を示し、転じて「正しい心」という意味を持つ漢字です。
ここから「徳」という言葉は、「人を敬服させ、感化させる力」や「他人に慕われる人柄」という意味を示すようになりました。
このため「不徳」は、そもそも徳が備わっていないことを表します。
「ある人の行いや心がけが立派でないこと」や、さらには「人が行うべき道に反すること」という意味になります。
一般的に、良い、正しいとされる行動の基準に当てはまらない状態も指します。
次に「致す」とは、「する」の丁寧な表現で通常は「致します」という形で使われます。
「頂戴致します」のように「~致します」と連用形で用いられることが多い言葉ですが、今回のように単独で使うとやや文語的な、いかめしい言い方になります。
最後の「ところ」は場所の意味ではなく、単に「ことがら」を示します。
例えば「私が関知するところではない」などと使います。
特定のものごとを指しているわけではないため、通常は平仮名書きにします。
ちなみに「不徳の」の「の」はこの場合、主語を受ける格助詞です。
こうしたことから、「不徳の致すところ」は、文字通りには「徳が足りないことが、引き起こすことがら」といった意味になります。
「自分に徳が備わっておらず、心がけが悪いため、こうした結果をもたらしてしまった」と、婉曲的に釈明する言い方ともいえます。
「不徳の致すところ」の正しい使い方は?
次に「不徳の致すところ」の正しい使い方について見ていきましょう。
「不徳の致すところ」は、多少とも自分と関わりのある事件や事故、失敗などについて責任を感じ、迷惑をかけた相手に謝罪する際の表現です。
また、自分と関係するあるものごとがうまく運ばなかった時、よくない結果となった場合などに、直接的に自分に原因があるわけではなくても、「関わった者として、善処できなかったことに自体に問題の一端はある」と、けんそんして遺憾の意を示す言い方でもあります。
そうした意味では、いかにも日本的な美徳や精神に満ちた表現の一つといえます。
欧米など海外では、「失敗したのは徳がないせいだ」という発想そのものが存在しないかもしれません。
このように「不徳の致すところ」は、へりくだっておわびしたり、残念さを表明する時の言い方ですから、自分や自分が属する組織などの側について使うのが一般的です。
ただ「不手際」「落ち度」といった直接のミスをわびる言葉とは異なり、「不徳」という、ある意味概念的な原因を持ち出しているわけですから、ビジネスシーンでは使う場面を選ぶ必要があります。
自分側の完全な手落ちが明確な場合には、かえって反感を買うことすらあります。
こうしたケースでは、むしろ原因を明示して明確、誠実にわびる文言を使うべきでしょう。
「不徳の致すところ」の類義語と例文は?
最後に「不徳の致すところ」の類義語と例文について見ていきましょう。
「不徳の致すところ」の類義語には次のようなものがあります。
◆類語
- 自分にも責任の一端がある
- 自分に非がある
- 日頃の不行状のせい
- 不摂生のため
- 不覚だった
- 不明を恥じる
- 覆水盆に返らず
「不徳の致すところ」の例文は次のようなものです。
◆例文
- このような事態になったのは、ひとえに私の不徳の致すところです。
- 今回の不祥事は自分の不徳の致すところであり、おわびします。
- 私がしっかりしていれば、もう少し結果は良くなったはずで、まさに不徳の致すところです。
「不徳の致すところ」の類義語や例文をご紹介しました。
類義語や例文を見るとより一層、理解が深まると思うので是非、参考にしてくださいね。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
「不徳の致すところ」の意味や正しい使い方、そして類義語や例文について詳しくご紹介しました。
出来ることなら普段あまり使いたくない言葉だと思いますが、もし使う際はこの記事を参考にしてもらえたらと思います。