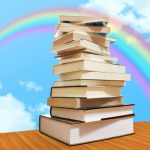日常生活の中で「舌足らず(したたらず)」という言葉をよく使ったり聞いたりしますか?
「舌足らずなしゃべり方」などとよく聞いたことはありますが、どんな場面で使うのか、そしてどんな意味合いがある言葉なのか気になりますよね。
そんな本日は「舌足らず」の詳しい意味と正しい使い方、そして類語や例文について詳しく解説していきましょう。
「舌足らず」の意味は?
まず最初は「舌足らず(したたらず)」の意味について見ていきましょう。
「舌足らず」という言葉は、口の器官である「舌」に「少ない・短い」という意味の「足らず」が付いた、名詞あるいは形容動詞です。
「舌不足」と漢字で書くこともありますね。
「舌」という漢字は、「干」という字の下に「口」が付く形になっていて、干にはもともと「おかす」という意味があります。
「舌」とは「口の中を押しのけるもの」といった意味合いから成り立っていると考えられます。
字の形自体がいかにもベロベロとした舌の形状をよく表していますね。
舌は、しゃべったり、話したりする行為には欠かせない器官で、顔の表情をつくることにも重要な役割を果たしています。
また食べることや、味わうことにも深く関わる機能を持っています。
こうした特徴的な、目立つ部分だけに、主に発話に関して多くの比喩的な慣用語句があります。
例えば「舌が回る」、「舌先三寸」、「舌打ち」、「舌を出す」、「舌を巻く」、「舌が肥える」などです。
こうした慣用的な言い方の一つが、この「舌足らず」です。
文字通りには「舌の長さが短い」ということを示しますので、「短いために、舌の動きが滑らかではなく、物言いがはっきり聞こえないこと」といった意味を表します。
あるいは「言葉で表現することがうまくない」といった意味合いもあります。
これらは、直接的に話し方の状態を表現する用法です。例えば「彼女のちょっと舌足らずなしゃべり方がかわいい」といった使い方です。
「舌足らず」にはもう一つ、比喩的に「発言の内容の言葉が不足しており、よく理解できない」、「言いたいことが十分言い尽くされていない」、「表現が不十分だ」という意味もあります。
こちらは話の内容に関して、不十分さを指し示す言い方です。
現在のビジネスシーンや一般的な会話の中では、この二番目の意味での用例がもっぱらだといえるでしょう。
「舌足らず」の使い方は?
次に「舌足らず」の正しい使い方について見ていきましょう。
「舌足らず」はビジネスなどの一般的な場面では、「言葉や表現が不十分で、よく言い表せていない」という意味合いでの使用が多いといえます。
特には、自分や自分の側の組織について、説明不足なことをおわびする際に表現することが通例です。
もちろん相手の行動に対して使うこともできますが、その場合は「そのような説明ではあまり理解できない」と、非難する言い方になります。
通常は、取引上や顧客への対応などの中で、行き違いなどがあって相手からクレームを受けたような際に「この前の説明は舌足らずでした」とおわびする際の表現として、よく用いられます。
直接的に「説明の仕方が悪かったです」と言い表すよりも、「やや言葉を省きすぎて、十分伝わらなかった」と、その行為が決してわざとや怠慢からではなかったのだと釈明し、ある程度の誠意を示す言い方だともいえるでしょう。
「舌足らず」の類語と例文は?
最後に「舌足らず」の類語と例文について見ていきましょう。
「舌足らず」の類語には次のようなものがあります。
「表現がまずかった」といった意味合いでは、、
- 言葉足らず
- 説明不足
- 説明不十分
- 言い足りない
- 言い尽くせない
- 口下手
などとなります。
また「発音や話し方が下手である」という趣旨では、、
- 話下手
- 訥弁
- しどろもどろ
- ろれつが回らない
- 口ごもる
- たどたどしい
などが挙げられます。
「舌足らず」の例文としては次のようなものが挙げられます。
◆例文
- 最近の若い人には、舌足らずなしゃべり方をする人が多いですね。
- 舌足らずな文章で分かりにくく、まことに申し訳ありません。
- 先日の私どものご説明が舌足らずだったため、誤解を招きご迷惑をおかけしました。
- これは少し舌足らずな論説で、読み応えに欠けるな。
「舌足らず」の類語と例文をまとめてご紹介しました。
是非、参考にしてくださいね。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
「舌足らず(したたらず)」の詳しい意味と正しい使い方、そして類語や例文についてご紹介しました。
発音が悪く微妙に伝わりづらい様子、そして表現方法があまり定かではない様子、ふたつの場面でしっかりと使い分けるようにしましょう。