
みなさんは日々の生活の中で「所以(ゆえん)」という言葉を見聞きしたりしますか?
「所以」「由縁」「由来」など似たような言葉もたくさんあるので使い分け方も難しそうな気がしますよね。
「所以」はどのような場面で使う言葉なのか、そしてどんな意味合いがある言葉なのかも気になります。
そんな本日は「所以(ゆえん)」の意味と正しい使い方、そして類語や例文について詳しく解説したいと思います。
「所以(ゆえん)」の意味は?
まず最初に「所以(ゆえん)」の意味について見ていきましょう。
「所以(ゆえん)」という言葉は、一般には文の末尾に付ける名詞です。
「所以」はもともとは、漢文を訓読した「故(ゆえ)になり」から派生した語ではないかとされています。
「故」とは「理由」という意味で、「故に」とすると、前段に原因を述べ、この言葉の後に結果を述べる接続的な言い方となります。
「だから」や「したがって」などと同じ用法です。
そして「故になり」は「~の理由である」という意味合いを示します。
これが時代が下る中で音変化を起こし、「ゆえんなり」と変わり、さらに「ゆえん」という名詞になっていったと考えられます。
古語では「ゆゑん」という旧仮名遣いが使われていたようです。
こうした由来から、「ゆえん」は「理由」や「わけ」と同じ意味の名詞となります。
ただ、「理由」などと比べると、古語から派生した言葉だけにやや古めかしい印象のある表現です。
では「ゆえん」を書き表す「所以」という漢字表記はどこから来たのでしょうか。
これも一説では、漢文を訓読みで読み下した「以て○○する所となる」から当てはめられたとされます。
この語句も「故なり」と同じく「~によって○○になった」といったように、原因と結果を示す表現です。
また中国語の「所以」をそのまま漢字としたのではないか、との見方もあります。
これは中国語で「スオーイー」と発音し、意味は「ゆえん」と同じ「理由」だからです。
「所以(ゆえん)」の使い方は?
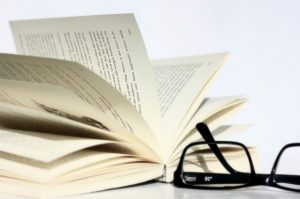
次に「所以」の正しい使い方について見ていきましょう。
前述のように、「ゆえん」は「理由」、「わけ」という意味の名詞ですので、冒頭に述べたように一般には「~である所以」、「~した所以」のように文の末尾に付ける用法となります。
語感が似ていることもあり、「所以(ゆえん)」は「由来」や「由縁」という言葉と混同することがありがちです。
由来の意味は?
「由来」という言葉は「由って(よって)来たる」という文から来た語だと考えられ、「物事がいつ,何から起こり,どのようにして現在まで伝えられてきたかということ」や、「○○にちなんでいる」ということを表します。
つまり「起源・歴史」や「いわれ」という意味です。
由縁の意味は?
また「由縁」も「由来」と近く、「起源」や「歴史」を示します。
「縁起」という言葉と似ています。
このため「由来」や「由縁」は、例えば「この神社が創建された由縁は~」や「千葉という地名の由来は」などと使われます。
あるいは「私の名前は父が尊敬していた先生に由来しているそうだ」などと、下に助動詞「する」を付加して動詞化した言い方もされます。
これに対し「ゆえん」は「理由」という意味であり、「これまでの経緯や歴史」という意味合いは含みません。
このため「ゆえんする」という言い方は誤用となります。
例えば「チームの敗北は監督の采配ミスに所以する」は間違いですし、「由来する」と言い換えても意味上からは不適切です。
こうした場合は「~が原因だ」、「~が理由だ」などとシンプルに述べるべきでしょう。
「所以(ゆえん)」の類語と例文を教えて?
最後に「所以(ゆえん)」の類語と例文についてご紹介したいと思います。
「所以(ゆえん)」の類語には次のようなものがあります。
◆類語
- 理由
- わけ
- いわく
- いわれ
- 事由
- 理屈
- 根拠
- 一理
- 筋合い
- 裏付け
- 証左
- 証拠
- 証し
などがありますね。
「所以(ゆえん)」の例文としては次のようなものが挙げられます。
◆例文
- 人の人たる所以は何だと思いますか。
- 彼が好かれる所以は、底抜けの明るさにあります。
- 彼を不世出の作家とする所以はここにある。
「所以」の類語と例文をまとめてご紹介したので是非、参考にしてみてくださいね。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
「所以(ゆえん)」の意味と正しい使い方、そして類語や例文について詳しくご紹介しました。
「所以」「由縁」「由来」との違いや使い分け方も分かったと思うので、もし活用する機会がありましたら参考にしてくださいね。
言葉の奥深さや難しさなどを改めて考えさせられるなと思います。







