
みなさんは日々の生活の中で「なかんずく」という言葉見たり聞いたりしますか?
恐らくあまり見聞きしないという人の方が多いかもしれませんね。
そんな本日は「なかんずく」の意味と使い方、そして類語と例文について詳しく解説したいと思います。
「なかんずく」の意味は?
まず最初に「なかんずく」の意味を見ていきましょう。
「なかんずく」という言葉は、漢字では「就中」と表記します。
これは副詞で、後に続く文を修飾し強調する働きをします。
「就中」の「就」という字は、会意文字です。
「京」と「尤」という字から成り立っています。
「京」とは、「高い丘の上に建つ建物」の形を元来は意味します。
また「尤」は「犬」の形を表し、そもそもは「身分の高い人の家に飼われた番犬」を意味したとされます。
こうしたことから、「就」は「建物につく番犬」、すなわち「つく」、「つき従う」を示す字になったと考えられます。
また「就中」の「中」は指事文字です。
そもそもは「軍隊の中央に立てる旗」の形を表したとされ、そこから「うち」や「内側」を意味する「中」という漢字が成り立ちました。
「就中」は元来は漢語であり、日本語にすると「中に就く」という意味を示す語句であると考えられます。
「中に就く」、すなわち訓読みにすると「なかにつく」ということから、これが音便化して「なかんつく」、さらに「なかんずく」と時代を経るに従って変化したと思われます。
「なかんずく」の意味は「その中でも」や「とりわけ」といったことになります。
これは現代中国語でも同じで、「就中」という副詞は「jiùzhōng」と発音され、文字通りの「間に立って、中に入って」という意味のほかに、「中でも、とりわけ」という意味合いがあります。
「なかんずく」の正しい使い方は?
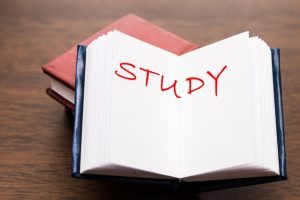
次に「なかんずく」の正しい使い方を見ていきましょう。
このように「なかんずく」は、元来は漢語の「就中」を訓読みで読み下したものが、そのまま日本語として援用されるようになった言葉であり、かなり堅い、文語的な表現だと言えます。
このため主には会話ではなく、手紙、小説、書面などの書き言葉として使用されるものだといえるでしょう。
「なかんずく」は、言葉の成り立ちから示されるように、「多くの物事の中から、特に一つを取り立てるさま」や「明確に、特に他から優れて区別されている様子」といったニュアンスを表す言い方です。
このため、一般的には、悪いことをあげつらって指摘する用法というよりも、他のことよりも際立っている素晴らしいもの、あるいは良いことを評価する際に用いる言い方だといえます。
いずれにしても、文章語的な表現であり、通常の会話ややり取りではあまり使用頻度は多くありません。
なお言葉の成り立ち、つまり漢文訓読の由来に従って、「なかんずく」は「なかんづく」と仮名表記される場合もありますが、これは「恥づかしい」などとは異なり、仮名遣いの間違いではありません。
「なかんずく」の類語と例文を教えて?
最後に「なかんずく」の類語と例文をご紹介したいと思います。
「なかんずく」の類語としては、次のようなものが挙げられます。
「通常よりも目立って、大きな程度や範囲に」といった意味を示す言葉としては、「格段に」、「特に」、「分けても」、「別して」、「一段と」、「殊に」、「特別に」、「ことさら」、「ひときわ」などです。
「他のすべての考察に加えて」といった意味では、「先ず」、「何はさておき」、「取り立てて」、「中でも」、「数ある中で」、「別して」などとなるでしょう。
また「なかんずく」の例文としては、次のようなものがあります。
◆例文
- すべての学問が大事なことに変わりはないが、なかんずく語学は重要だろう。
- あの方は江戸文化全般、なかんずく元禄期の戯作に詳しい先生です。
- そうした傾向は、なかんずく晩年の作品に目立つと言える。
「なかんずく」の類語と例文をまとめてご紹介しました。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
「なかんずく」の意味と正しい使い方、そして類語と例文をご紹介しました。
おさらいをすると「なかんずく」の意味は「その中でも」や「とりわけ」になります。
漢字で書く場合は「就中」となるので覚えておくと良いでしょう!







