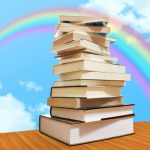みなさんは日々生活している中で「幾久しく」という言葉を使ったりしますか?
「幾久しく」と書いて“イクヒサシク”と読みますね。
読み方も少し難しい言葉ですが、どんな意味合いがある表現方法なのでしょうか。
そんな本日は「幾久しく」の意味と正しい使い方、そして結納や結婚式で使う場合の例文についてご紹介したいと思います。
「幾久しく」の意味は?
まず最初に「幾久しく」の意味について見ていきましょう。
「幾久しく」は、「幾久しい」という形容詞の連用形です。
しかし一般的には、「幾久しく」の形のまま副詞的に添えられる、強調の表現だといえます。
「幾久しく」は、日本書紀や万葉集の中にも見える、非常に古くから使われている「大和言葉」の一つです。
文語的な、雅やかな言い方で、現代は主には手紙やあいさつの中での言上で使用することがもっぱらです。
「幾久しく」は「いつまでも変わらないさま」、「将来も長く続くさま」を言い表します。
古い文献でも将来の時間の経過について述べる用法が多いようですが、中には「遠く隔たった昔のこと」といった意味を示すものもあるといいます。
「幾久しく」の「幾」は、「幾重にも折りたたんで」、「幾らでも食べるがいいよ」といった用例のように、「非常にたくさん」という状況を強調するものだといえます。
すなわち「久しく」という「時間的に長い間に」という言葉を、より強めている形です。
「幾久しく」の正しい使い方は?
次に「幾久しく」の正しい使い方について見ていきましょう。
「幾久しく」は現代では、主としておめでたい祝典や儀式などの場で、あいさつとして言上する文言の中や、そうした催し物への招待状、お礼状といった書面の中で使用されることが多い言葉です。
元来が奈良時代より以前からある古い表現ですので、古来の宮廷文化にちなんだような雅やかなイメージで、おめでたい場を言祝ぐ、慶事には欠かせない用語だといえるでしょう。
「幾久しく」のように、やや格式張ったお祝いのシーンでの、「末永く」と強調する慶賀的な表現としては、ほかに「千古不易に」、「常しえに(とこしえに)」、「弛みなく(たゆみなく)」、「悠久の」、「久遠の」、「長久の」といった言葉があります。
「千古不易」とは「永遠に変わらないさま」を示し、「万代不易」、「千古不変」などとも言いますが、いずれもかなりかしこまった表現です。
やはりこうした言葉の中では、語感の柔らかさや分かりやすさ、発語のしやすさも手伝い、「幾久しく」が最も使われることの多い言い方だといえるでしょう。
「幾久しく」は、こうしたお祝い事でのいわば「定番」的な表現ですので、逆に言うと「悪い出来事」や「不幸なものごと」について使用することは、通常ありません。
例えば「幾久しく不運なことが続く」といった言い方は適切ではないといえます。
結納や結婚式で「幾久しく」を使う場合の例文は?
最後に「幾久しく」を結納や結婚式で使う場合の例文をご紹介したいと思います。
どんな方にも身近な「お祝い事」の代表的な儀礼としては、やはり結納や結婚式が挙げられるでしょう。
近年は、結婚の儀式自体を西洋式なスタイルで行うことが好まれたり、あるいは日本の伝統に縛られず、自由な発想や企画で実施する若い方々が増えてきており、昔ながらに両家一同がうち揃って、結納の儀式を交わす事例は少なくなっているかもしれません。
ただ日本の古くからの習わしとしては、「幾久しく」は結婚や結納の儀礼においては欠かせない、非常に大事な言葉だといえます。
一般的に、結納の際には、まず結納品を贈る側が「幾久しくお納めください」と口上を述べ、受け取る側は「幾久しくお受け致します」と答えるとされています。
文字通りに解釈すると、日本語の文法的にはやや意味が通らないやり取りですが、この場合の「幾久しく」はあくまで「いつまでも末永く、二人の愛に満ちた関係が続きますように」と縁起を担ぎ、定型的に言い添える祝言だといえます。
また結婚式でも、二人を祝福するスピーチの際などには「幾久しくお幸せにお暮らし下さい」、あるいは「幾久しく、お二人に幸多かれとお祈り申し上げます」、「お二人の輝く愛が幾久しく続きますよう、心から願っております」などと申し添えることが一般的です。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
「幾久しく」の意味と正しい使い方、そして結納や結婚式で使う場合の例文について詳しくご紹介しました。
結納や結婚式で使う際の例文などを参考にして頂くと、正しい認識で活用することが出来ると思います。
古くからある表現方法なので、意味をしっかりと理解して正しい使い方で相手に伝えたいものですね。